森とレジリエンスから、3つのコモンズ再生へ
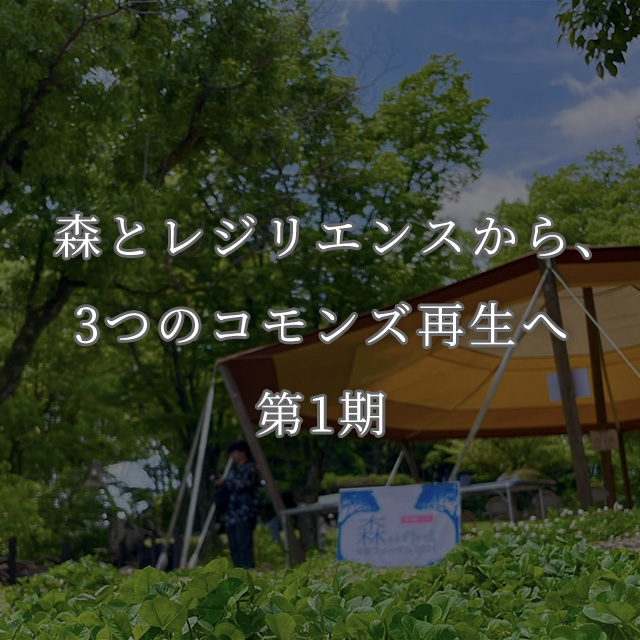
エッセンス
トリプルコモンズとは、平たくいいますと、たとえば気候変動/生物多様性/防災、と切り離すのではなく、三本の矢を地域コミュニティのレジリエンスを軸にして、より良い方向に進む道筋を探し、すべてのいきものがイキイキする環境を創り出していこう、というものです。その足掛かりとして、公共空間で食べられる森づくりを増やす、を具体的な指標の1つにしています。
それぞれの普段のメンバーの活動の軸足は様々ですが、地域やコミュニティの「枠」を超えて重なる問題意識をつなぎあわせ、それぞれの取り組みのエッセンスを束ねながら、「相乗作用」を創り出す―がこのトリプルコモンズの大事なアプローチになっています。2024年6月からはじまったこの自主プロジェクトの第一期(種まき期間)を経て、第二期から少しそのギアを上げていきたいと思います。
プロジェクトの背景と趣旨
森とレジリエンスから、3つのコモンズ再生へ
〜つながりの質を育む「レジリエンス文化」を広める〜
生物多様性の劣化は30年以上前から科学者が警告を発し、国際会議でも主要な議題としてとりあげられ、国の政策も色々ありますが、総体としてずっと劣化の勢いが止まりません。ある指標では限界(Tipping Point)を超えているという研究もあります。一方で、ある国のアンケート調査によると、生物多様性については知っているつもりだけれどよくわからない、という回答が多い傾向になっています。
また生物多様性関連の問題は、単独であるのでなくて、気候変動や森の在り様、地域との関わり、人々の暮らしとの関わり、災害、というように、自然―人との関係性と密接に関わりがあります。とはいえ、多くの場合、頭で知ったつもりになっていても、わたしたちに、わたしたちの暮らしにどう関わっているのか、身体で捉えないと、実感が湧いてきませんよね、きっと。
そこで、食べられる森を、公園や校庭、放置された土地につくり、自然共有サイトとして協働で成熟化させていくことによって、負の連鎖を正の連鎖に変えていくモデルになるのではないかー。つまり、「食べられる森を創る≒生態「系」の在りようを体得する≒生物多様性の本質に気づく→その本質への気づきが、土地の使い方、食糧の選び方、暮らし方の変容につながる」そういう正の連鎖を共に創り上げようというのが、このプロジェクトです。そういった食べられる森を増やすことをひとつの指標にして(場所によって、森の中の放置された木々の再生など、様々な形があると思います)、地球社会レジリエンスセンター(GCRC)とその仲間たちは協奏しながら、アクションを興していきます。
概要
枠組み
このプロジェクトでは、全国の空き地に、「食べられる森」を介して自然共生サイトを推進しながらレジリエンスを育む仕組みとして
- 「森とレジリエンス学校(*1)」を創ること
- 「3つのコモンズ(*2)」を同時に育み、再生・更新すること
- 次世代につなぐレジリエンス文化モデルを創ること
を主眼にしています。これを通して、つながりの質を育む「レジリエンス文化」を広めることを目指します。
*1:森とレジリエンス学校
- 森とレジリエンスをテーマに、子供から大人まで参加できる教育プログラムを提供
- 「食べられる森」実践者らと共に、「3つのコモンズ再生のための共有地」を創るためのワークショップの実施
- 学びを伝えることに軸を置いたナラティブ・ビジュアル手法を介して、森とレジリエンスのエッセンスを全国に広げる
*2:3つのコモンズ(通称:トリプルコモンズ)
私たちの暮らしや営みや命にかかわるものを、バラバラではなく相乗作用を興しながら守り、育てていく。たとえば…
-
1:コミュニティ・ウェルビーイング
地域コミュニティの人たちが集まり、共に「食べられる森」を育てることを通して、コミュニティを育み、子供からお年寄りまで世代間を超えて、人と人の繋がり、人と自然の繋がりを大切にし、人の心やウェルビーイングに寄り添う場を育み、再生する。
-
2:気候変動対応・生物多様性
生態系と人と社会についてのつながりを体感し、気候変動や生物多様性と私たちの暮らしの関係について学び合い、協働知を育み、再生する。
-
3:防災・暮らし
今あるもの(地域が大切に守ってきたもの、地域に根付いてきたもの)あるいはその智慧を使って工夫してつくりあげるもの(例:井戸水や石窯を使って料理をするなど)を通して、何か災害が起きても暮らしを守る手立てを育み、再生する。
プロジェクト全体の流れ
第1期は、第1ステップ、および第2ステップを中心に実施予定です。
第1ステップ(起)
「森とレジリエンス 京都フォーラム 2024」と「森とレジリエンス 神奈川フォーラム 2025」から引き出される「気づき」を集約した、トリプルコモンズの仲間を増やすための冊子を、ナラティブビジュアル手法で製作します。
また、参画メンバーがその他の地域で実施している(これから実施していく)取り組みから引き出される知見や気づきも、ここに集約していく予定です。
さらに、本プロジェクトのテーマを軸に、地域、組織、専門といった枠を超えて対話を可能にするための森とレジリエンスフォーラムを継続的に開催し、これに関わる共通理解や取り組みを進化/深化させていきます。
第2ステップ(承)
「食べられる森」実践者と共に、「3つのコモンズ再生のための共有地」のプロトタイプを、参加者との協働対話を介して、また相乗効果について実証実験を行い、可視化をしながら、先進例としてつくりあげます。まずは京都からスタートします。
参画メンバーから提案があれば、その他の地域で展開する仕組みをつくる計画です。このようにして森とレジリエンスを軸とする自然共有サイトを増やしながら、互いに実施状況や知見を共有し、協働知につなげていく仕組みを整えていきます。
第3ステップ(転)
異なる地域コミュニティの空き地に、「3つのコモンズ再生のための共有地」を推進し、レジリエンスの視点を交え、つながりの質を高めるプロセスを協働で学ぶ仕組み「森とレジリエンス学校」を創ります。その際、多様な現場の実践者、学生、自治体、研究者などが協働できるように仕組みをデザインしていきます。
第4ステップ(結)
第1~第3ステップを通して、レジリエンス文化を広げます。
プロジェクト期間
- 第2期(2025年6月~2026年6月)
- 第1期(2024年6月~2025年6月)
体制
プロジェクト参画メンバーを募集します
以下のA、または(および)B、C、Dのカテゴリーから、ご自身にピッタリ合うものを選択ください
A:実践メンバー
プロジェクト実践(空き地に食べられる森創り、森とレジリエンス学校実施)に参画してくださる方
- プロボノ
- プロフェッショナル(最初はプロボノでお願いすることになると思いますが、今後助成金や寄付金を集める中で、人件費等を捻出していきたいと思います)
B:財政サポート(法人/団体)メンバー
年間1口(5万円)~でサポート
C:応援(個人)メンバー
年間1口(1万円)~でサポート
D:その他支援
プロジェクトメンバーの方には、随時プロジェクトの動き、活動について、ご報告/ご案内メールを差し上げます。また本プロジェクト関連のイベントの際には無料でご招待します、さらに、本プロジェクトから生み出されるナラティブビジュアル冊子やオリジナルグッズなども、ご貢献にあわせてお贈りさせていただきます。なお、法人/団体につきましては、依頼に応じて、本プロジェクトから引き出される知見を生物多様性やSDGs等と関連させたオリジナルワークショップを別途開催することも可能です。
応募方法
I:参画いただけるすべてのみなさま
以下のフォームからご登録ください。
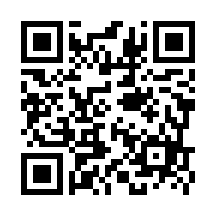
II:BまたはCでご参画いただけるみなさま
上記Iをお済ませの上、下記にお振込みをお願いします。
- 振込先
- 銀行名:京都信用金庫
店番:001
口座番号:3131611
口座名:シヤ)チキユウシヤカイレジリエンスセンター - 振込期日
- 2025年6月30日
参加メンバー(2024年9月現在/敬称略/50音順)
- 上田 耕佑
- 井上 英之
- 泉谷 雅吉
- 土田 亮
- 大村 淳
- 笠島 陽子
- 齋藤 夢果
- 櫻田 千江里
- 清水 美香
- 柴田 涼
- 土田 亮
- 新川 由希子
- 中村 元
- 西川 聖哲
- 野崎 真理子
- 本田 律
- 望月 亜希子
- 山口 有里
- 吉田 恵美子
- 吉田 茂
- 李 よんひ

