森とレジリエンス 屋久島編 2025
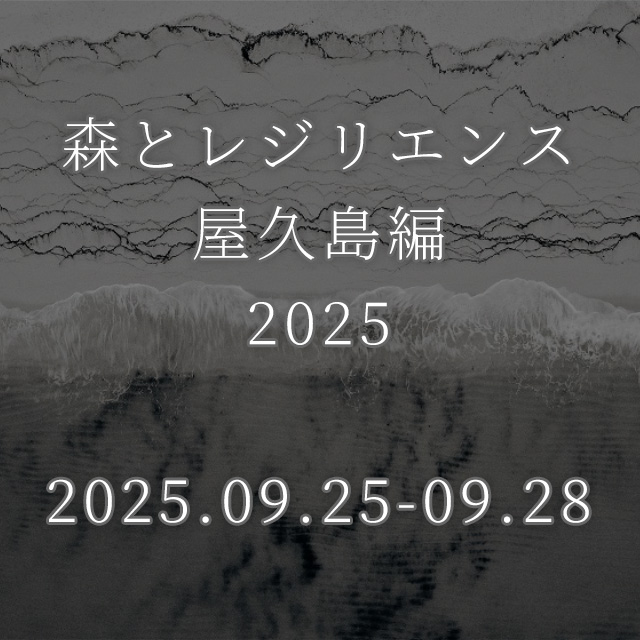
森とレジリエンス 屋久島編 2025
3泊4日のおとなフィールドワークツアー
GCRCとしては3回目。今年のテーマは「右脳と左脳の交差点」。情報に溢れた世の中の中で偏りがちな頭の使い方を、里と森の境界の中で感性や身体と共にバランスを整えるプラグラムを用意しています。右脳と左脳のバランスを整えてこそ、気候変動時代もAI時代も、きっと乗り越えていける、その入口に立つプログラムでもあります。
このプログラムは元々、京都大学で実施してきたSDGsとレジリエンス思考に関わるプログラム(屋久島における「木を見て森も見る」SDGs思考養成実践モデル事業/文科省2020年度SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)をプロトタイプとし、それを一般的な文脈に落としこんでアップデートして実施しています。
幅広い方々に、屋久島を舞台に「自然~人間~社会の関係性」、自然~人間~地域(コミュニティ)の中に宿る「レジリエンス」を体得し、自然と共生する持続可能な社会のための「つながり」の再生を念頭に、みなさまの暮らしや仕事場、そして生き方に活かしていただきたいという想いから生まれました。
数多くある野外プログラムの中で、なぜ屋久島なの?そしてなぜここでレジリエンスの本質の体得につながるの?そのような問いへの応答のヒントは、屋久島の自然の中で木と木の関係性をはじめ、無尽に見られる生態系の関係性の中で見つけられるでしょう。少しそれを紐解きますと…
1:屋久島の原始的(Primitive)な自然の中に見られる関係性の奥はとても深く、他ではなかなか出会えないものとなります。だからこそ、森と人の相互性としてのレジリエンスの本質について、身体から得られることにつながっていきます。
2:さらに屋久島には、言葉で解説するよりも確実に伝わるであろう「森~里~川~浜~海」のつながりがそこに在ります。しかしそれは当たり前にあるわけではなく、私たちが日々の暮らしの中で無意識に分断してきたものに関係します。そこから、私や日常の暮らしや営みを振り返ることで、レジリエンスの本質の体得に向かいます。それは、SDGsのための人間自身の変容に不可欠な出発点となります。
こうした側面から得られる気づきを、自然と共に生きる私たち人間社会の持続可能性に向けて、それぞれのアプローチに織り込んでいくことができます。右脳と左脳の両方をめいっぱい使うプログラムです。
他には類をみない、レジリエントで持続可能な社会を研究する研究者と森の人・実践者が協働し、試しながら磨き続けているプログラムでもあります。
イベント詳細
| 開催日時 | 2025年9月25日(木)〜2025年9月28日(日) 3泊4日 |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人地球社会レジリエンスセンター |
| 講師 | 清水美香(サステナビリティ研究者)、田平拓也(森のスペシャリスト) |
| 対象 | 企業人、団体職員、学校/自治体関係者、学生 |
| 参加費 | ・GCRC会員の方:10万円(税込)(できるかぎり7月31日までにお振込みください) ・一般の方:12万円(税込) ※2025年7月31日までにお振込みの場合、早割として1万円OFFとなります ※個人会員への入会手続き ※7月31日午前10時の時点で最小催行人数3名に達しない場合、中止とします(それまでにお振込みいただいた参加費用は全額返金いたします) 宿泊費(宿泊はこちらでまとめて手配します。1日はキャンプ野外泊で無料、その他は1泊8,000円~1万円程度)および渡航費(ご自身で屋久島空港までご手配ください)が別途必要です。 |
| キャンセル料 | 2025年8月20日まで50%、2025年8月21日以降は100% |
| 定員 | 数名(最少催行人数3人) 実施が決定いたしました最少催行人数(入金済み)に達したときに催行決定とします |
| 申込方法 | 参加をご希望の方は、名前、所属(ある方のみ)、電話番号、メールアドレス、住所を書いて、メールタイトルに「森とレジリエンス屋久島 2025 参加希望」と記載し、一般社団法人地球社会レジリエンスセンターのメールアドレス(contact@gcrc.or.jp)までお申し込みください。こちらから確認のメールをお送りする際に、参加費の入金方法や注意事項などをお知らせいたします。 |
| 申込期限 | 2025年8月12日(火) |
タイムテーブル
1日目:森との出会い―感覚をひらく一日
- 09:25|屋久島空港着、galleryTABIRAへ移動
オリエンテーション
「森とレジリエンスとは」―屋久島を舞台に、五感と思考の旅が始まる。
地杉の森散策(樹齢50年)
地域に根づいた森の記憶をたどり、風景と身体を調律する。
森の読書会×茶室セッション
本と茶を媒介に、森の静けさと対話する時間。
森のサウンドスケープ
自然の音に耳を澄まし、「聴き合う力」を取り戻す。 - 17:30|夕食@galleryTABIRA
- 20:00|解散
2日目:森をめぐり、森に泊まる―「水と循環」の日
- 05:30|お宿発
春田浜にて日の出(海抜0m)
東の水平線から始まる一日―光、波、そして呼吸。
松峰大橋(安房川)~ヤクスギランドへ
屋久島の水系をたどり、森の構造と循環を観る。
森の案内
「水の流域」「森の遷移」など、左脳で理解し、右脳で感じる解説。
天空の茶室
標高1,000mを超える空間で、感性の静寂に触れる。
森のサウンドスケープ
苔、風、雫。森が奏でる響きの中に身を置く。 - 11:30|森歩き(片道1.5km/約45分)、淀川小屋着
森とレジリエンス・ワークショップ(1)
テーマ:「循環とつながりを感じる身体と思考」
森の中で、自然と自分の関係性を更新する。
おとなキャンプ(1泊)
焚火と語らいの中で、自分の内にある右脳をひらく。
3日目:森の深層へ―時間とスケールを体得する日
- 05:00|森の目覚め × サウンドスケープ
朝の森の息づかいを、音と気配で受け取る。 - 10:00|1500年の巨樹の前で「天空の茶室」
悠久の時間を抱く木と向き合い、自身の内面と対話する。
森歩き(復路) - 13:00|galleryTABIRA着
森とレジリエンス・ワークショップ(2)
テーマ:「木を見て森を見て、【隙間】をデザインする」
森での体験から得た気づきをもとに、地域や社会の課題をあらためて眺め直す時間。個人と全体、部分と構造、見えるものと見えないもの。右脳と左脳の両方を使いながら、「木を見て森を見て」、そのあいだにある境界、そして「隙間」に目を向け、共に未来の可能性を形にしていく共創のプロセス。 - 16:30|宿へ移動、夕食、自由解散
4日目:いのちとつながりの足跡をたどる日
- 05:30|移動開始
永田いなか浜
ウミガメの産卵地。命のリズムと海とのつながりを観察。
西部林道経由 森のドライブ
ガジュマル、アコウ、ヤクザル、ヤクジカ―生態系との出会い。 - 08:00|大川の滝
水の循環を五感で感じるひととき。 - 10:30|アートワークセッション
「右脳×左脳」から生まれた気づきを、形に。 - 12:00|終了・解散
終了後、昼食(各自)や離島の港空港島へ送迎致します。
悪天候の場合
台風の影響等から大雨、洪水が予測される際には、日程を延期して実施いたします。中止の判断についてはこちらからお知らせいたします。その後の日程についても改めてお知らせいたします。
なお、線状降水帯については予測が難しい側面もあるため、事前に判断しかねることもあります。滞在中にそのようなことが起きた場合は、出来る限り安全な場所に避難するなどの措置をとります。予定の遅延などが起こり得ることはご了承ください。
ご注意
- 万が一、既に入金していただいて、最少催行人数に達さない場合、速やかに全額をご返金いたします。一方、締め切り日を待たず募集終了の可能性もありますので、早めのお申込みをおすすめします
- ご都合により、参加日数が少なくなる場合などはお問い合わせください
- その他、参加にあたって、ご不明点、ご質問ありましたら、お問い合わせフォームかcontact@gcrc.or.jpまでお問い合わせください
参加申込
申込方法
参加をご希望の方は、名前、所属(ある方のみ)、電話番号、メールアドレス、住所を書いて、メールタイトルに「森とレジリエンス屋久島参加希望」と記載し、一般社団法人地球社会レジリエンスセンターのメールアドレス(contact@gcrc.or.jp)までお申し込みください。こちらから確認のメールをお送りする際に、参加費の入金方法や注意事項などをお知らせいたします。
「森とレジリエンス 屋久島編 2024」参加者の感想
R.Nさん
屋久島での「森とレジリエンスSDGsフィールドワークツアー」では、自然の中での体験を通して、レジリエンスの本質を深く理解する貴重な学びとなりました。森、里、川、海が織りなすつながりを全身で感じる中で、自分の日常生活がいかに自然との関係を無意識に分断しているかに気づかされました。屋久島の原始的な自然環境の中で、他では得難い豊かな生態系の相互関係を目の当たりにし、森と人との関係性や自然と社会とのつながりの重要性が五感を通じて認識することができました。このプログラムは、単なる理論的な学びではなく、心と体でレジリエンスを体得する独自のアプローチが特徴的でした。日常の暮らしを見直し、自然と共生する未来への道を切り開くための気づきを屋久島で見つけることができ、大変有意義な時間となりました。
T.Iさん
個人的に大好きな屋久島。渡島の回数はもう分からない程だが、今回あえてプログラムへの参加を決めたのは、“自分以外”を通して、誰かとの対話や空気感を通して感じる屋久島から、なにか新しい気づきを受け取れるようなワクワクした気持ちがあったからである。「いつもの屋久島の過ごし方」は、山や森を歩き、海・川で遊び、自然との繋がりや自然の在り方から得られるものを受け取って、自然と涙が出たり、笑顔になったり。屋久島という場所が、「わたしという個」によりフォーカスする為に最適な存在で、自分の内と外を循環させるために必然だったように思う。
そんな「いつもの屋久島の過ごし方」があった私の中で、先ず新しい気づきをもたらしてくれたのがヤクスギランドでの天空の茶室。人間が創った文化・道・様式、人が生きるため、たのしむために大切にされてきた心や智慧を、お茶を相手の為に点て合うというカタチで体感。自然や人から感じる音・リズム、空気の振動、大小たくさんのいのちに包まれながら初対面の誰かと対話をたのしむ。お相手とは短い時間ながらも、茶道の所作で大切な【一度に二つのことをしない】【ひとつひとつの動作を大切にする】というキーワードを受け取り、それが自分のこれまでの日常を捉え直すヒントになった。どれだけ多くのことを効率良く行うかが重要視されがちな昨今は、モノ・コトひとつひとつを丁寧に扱い、時間を掛けることは減り、日々頭と指先で情報を得ている気になっている事が多いように思う。圧倒的に頭でっかちで、身体が置き去りのように思う。自分自身を振り返っても、ついつい先回りして効率的思考を巡らす癖が根深くある。効率を追求することは決して悪ではないが、その前に先ずは【ひとつひとつの動作を大切にする】があってもいい。そこにあるストーリーに五感を傾け、見つめる。面倒だと思うことも丁寧に織りなしていくプロセスをたのしむ。ゆっくりと自分を内観・内省し、道具や人、環境に意識を広げていくと、今の自分に繋がる新しい発見がある。茶の道にしても、チャノキの栽培から道具が生まれるまで、湧かした川の水はどこからどう流れてきたのか、お茶をたのしむ相手はどんな生き方をしているのか、それだけでも莫大で壮大なストーリーがあり、私たちはそれをたのしむ文化を既に持っているという素晴らしさに気が付いた。
地杉の加工場では、厳しい自然環境下で育った屋久島の杉の強さを知った。年輪の目の細かさや油分の多さなどは、長い歴史を持つ屋久杉の話として知っていたが、今現在屋久島でまさに育っている杉にもその特徴が受け継がれているとは。どんな環境で育つかで特徴が出て、変化に合わせて必要な進化もする。人間含め全ての生き物は同じだと感じた。災害を防ぐための伐採や、人口減や環境変化を見据えての植林、林業の智慧。その一方では里で暮らす人々の海・川・森離れもある。太古の森が存在する屋久島も、自然と人の境界が濃くなってきているのかもしれない。ここでもやはり「ストーリーに目を向け、知ること」が境界の自由な横断のステップとして重要なことなのだろうと感じるなか、地杉の染色を体験した。プログラムを通して頭に入れた情報が、今回は織物を染めるという行為によって、すっぽりと身体(細胞)のなかに内包された。身体を振動させ、揺らいで染みこませる。染みこんだものはなかなか消えない。時間や環境、混ざるもので結果が変わってくるのもまた面白い。身体を使うことは、やはり重要だ。
森の空気を吸い込みながら屋久島の人々と自然の今を知り、様々なナビゲートで知識を得たり文化を体感したり感覚として染みこませたりしながら1日を終えた。プログラムを通してあらゆるストーリーを知り、それが自分の中に入ってくると、自分という個だけでなく、個と全体・内と外・境界の重なりが在り在りと見えてくるように感じた。わたしという人間は全てと繋がって成り立っているなと、改めて感じた。自己調整の大切さをみなさんに伝えることを自分のライフワークとしている以上、当然頭ではわかっていて実践もできていると思っていたが、自然や文化、人から学び得られるものはまだまだあると感じるプログラムであった。出逢ったすべてのみなさんに感謝の思いだ。
匿名さん
屋久島での4日間を振り返って
初屋久島!4日間のプログラムを終え、写真で見ていた深い森から、空・川・滝・里・海と循環するなかに植物、動物、人間、山の神が在る立体的なイメージへと変わっていきました。「森には答えがある」という言葉を頼りに参加した私。参加する前は、森に入れば自分の中から答えが見えてくるのではと思っていましたが、実際は少し違っていました。私の心の中に残ったのは「感覚を取り戻す」場と時間の大切さでした。
1日目
前乗りしたおかげでプログラム前に、海に続く女川の中でお茶を飲むことができました。美しい水と苔の蒼さに見惚れながら、川と海は繋がっていることを実感。牛床詣所(うしどこもいしょ)では、苔むした祈りの場が200年も前から今も山岳信仰を支えていることを知りました。途中で出会った猿たちの生活感にも触れ、道沿いに咲く美しい白い花に見惚れ、「ウェルビーイング」について対話しました。
2日目
屋久杉ランドはその名に反して見応えがあり、土埋木が残る地を保存するために作られたとも知りました。千年杉や仏陀杉など1000年以上も前から、何種類もの苔と共に静かにそこに息づいています。長い歴史の中で他の植物と共生していたり、絡み合っていたり。「一番進化しているのは1年草」と知り、「進化」という言葉がこれまでのプラスのイメージから変わっていきました。「進化」というレースから外れた古代からそこに在る森になぜ私たちはこれほど惹かれるのだろうか、と考えさせられました。「天空の茶室」では森に囲まれ、水の音を聞きながら気持ちが解放されていきました。屋久島地杉加工センター見学では、引き継がれる、倒れた屋久杉を里へ運ぶ職人たちの技や思い、切られた木の山に新しい苗を植え森を守る人たち、製材し切り取られた端材や皮を再利用しようと知恵を絞りながらここで暮らす人たちの姿に触れました。杉の皮で染めたストールは一つ一つ違う色合いで心を癒してくれました。
3日目
大川の滝へ。激しく流れる滝を見上げながら、ただその音と水飛沫の中で時を過ごしました。屋久杉の森とは異なる緑の林道を通り抜け、鹿に出会い、ガジュマルの木に触れました。永田いなか浜では海と浜を行き来する亀を思い浮かべました。三日間のプログラムで感じたこと、考えたことを白い紙に表す時間がありました。私は古代から続く屋久島とそこに在る森や川、滝、海とそこに暮らす動物や人間、山の神が対話している様子を描きました。自分の今の生活と繋げて「感覚を取り戻す場や機会を創る」と書きました。
4日目
一枚板が覆い尽くす川で一人一人が思考する時間がありました。4日間を振り返り、今の自分と向き合う中で、私はなぜ「感覚を取り戻す場や機会を創る」としたのか、そもそもここに書いた「感覚」とは何を指すのか考えてみることにしました。
今の課題と屋久島での気づき
【私が今課題だと思っていること】は、ココミラ+の仲間と行っている不登校支援活動の中で、なかなか打ち破れない壁があることです。「今の学校の仕組みの中では、子どもたちの学ぶ楽しさは実現し難い。多様な学び場が必要であり、公教育そのものを考え直していく必要がある」という考えは、自分と同じ価値観で繋がるコミュニティーでは理解してもらえても、そこからなかなか広がらない現実に何度もぶち当たっています。そこで私はこれまでやってきたことを振り返ってみることにしました。
- ココミラ+の活動(支援者の研修会、「みんなの文化祭」、元不登校生のトークセッション、子どもに関するドキュメンタリー映画上映会&シェア会)
- 発達支援センター相談員として保護者や子どもの声を聞く
- スープ屋Hyggeでの出会い
さらにこれから自分がやりたいことを挙げてみました。
- こどもアドボカシーの学び
- こどもマーケットへの関わり
- 民設民営公民館「まる」(中高生の人生の寄り道の場)への関わり
- edible school yardの実現
- 各国の教育についての学び
なぜ私は「感覚を取り戻す場や機会を創る」としたのか?屋久島の中に息づく全てのものから気づかされていったさまざまな私の中の感覚。知識や情報を飛び越えて私の中に呼び起こされた感覚こそが私自身を変え、動かす原動力になったのではないかと思いました。私が今抱えている課題についてもそこに突破口があるように思えました。
天空の茶室で聞いた若者の将来に対する不安もある中、未来そのものである子どもたちの魅力に取り憑かれている私は、今の子どもたちの学校教育に対する私の課題を解決するヒントを屋久島プログラムの中から得たような気がしています。
感覚とは何か、そしてこれからの行動
私の課題に関して考えた「感覚」とは、
- 今の子どもと子どもだった昔の自分を受け止めること
- 〜したいと思う気持ちと行動に移すプロセスを楽しむこと
を指しています。もちろん、今の私には直ぐにその場や機会を創る力はありません。まずは自分自身がそんな場を体験し引き出しを増やすことから始めようと思います。
- 感覚を取り戻すさまざまな体験をする。
- 行動している大人や子どもと知り合う。
- 自分の体験や考えていることを仲間に伝え、共有する。
「隙間をデザインする」「木を見て森も見る」は「感覚を取り戻す場や機会を創る」までの過程に活かしていけたらと今は考えています。今回のプログラムで私が将来やっていきたいことも少し見えて来たような気もしています。

